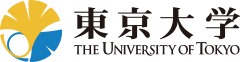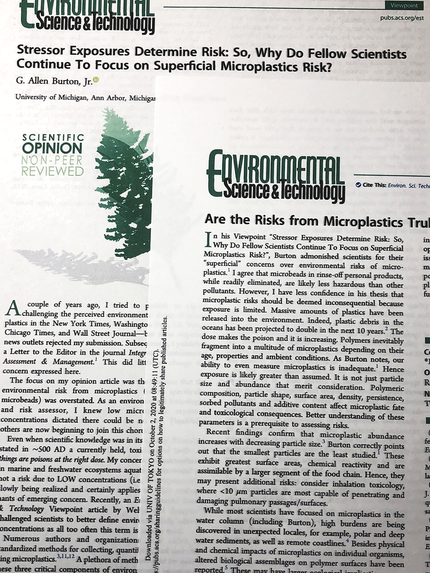マイクロプラスチックのリスク(危険性)は取るに足らない問題? ~環境科学者の議論から見るプラスチック汚染~
マイクロプラスチックが招くリスクはあるのか
プラスチック汚染の生物への影響を調べる実験では,生物に対し自然環境ではありえない量のマイクロプラスチック(大きさ5mm以下)を曝露(問題となる因子にさらすこと)させていることが多い。研究者の話を聞いたり,関係論文を読んだりしていると,「実験の曝露量が自然環境とはあまりにもかけはなれているのではないか」とひっかかった。なぜかとそのたびに思っていたのだが,研究者の間では実験だから結果が出やすい条件のもとで行うのは「常識」なのだろうと自分に言い聞かせていた。
ところが,プラスチック汚染に関する論文,書籍を渉猟していたら,学術誌にある興味を引く議論に遭遇した。「Environmental Science & Technology」(2017年11月17日発刊)で,米ミシガン大学のアレン・バートン(G. Allen Burton, Jr.)教授は,「有害因子への曝露がリスクを決める―なぜ仲間の科学者たちは取るに足らないマイクロプラスチックのリスクを重要視するのか?」という刺激的なタイトルの見解を載せていた。
「社会に広く受け入れられている「マイクロプラスチックの環境への脅威」論に対する反論を米国の著名な新聞に投稿しようと考えた。しかし,ニューヨーク・タイムズやワシントン・ポスト,ロサンゼルス・タイムズ,シカゴ・タイムズ,ウオールストリート・ジャーナルは投稿をボツにした。その後,環境の評価・管理に関する学術誌で意見を表明したが,ここに述べる懸念を改善する効果はほとんどなかった。」
長くマスメディアにいた者として,科学者の投稿を扱った経験もあるが,バートン教授の投稿は,失礼を承知で言えば,私もボツにしたと思う。なぜなら,新聞の読者は,科学者だけではなく,一般の人々がほとんどで,その人たちの実感と合わない内容の投稿を掲載することは難しいからだ。
では,そのバートン教授の主張はどういう内容なのか。
プラスチックのリスクは大げさに言われている
「マイクロプラスチック(マイクロビーズを指す)による環境リスクは大げさに言われている。環境毒性学者,リスク評価者から言えば,マイクロプラスチックの低濃度曝露ならリスクはないだろう。私だけでなく,そう考え始めている科学者もいる。
海洋や湖沼,河川などの水域環境におけるマイクロプラスチックは,低濃度(つまり低曝露)だからリスクにならない。低曝露はリスクでないということは,理解されてきているし,このことはほかの汚染物質にも当てはまる。
また,多くの論文著作者や組織は,マイクロプラスチックを集め,量を計り,特性を見極めるという3つの要素について,調べる基準となる標準的な方法の確立を呼びかけている。この3要素の評価法は数多くあり,それぞれ長所と短所がある。しかし,どれも十分とは言えない。数多くの「偽影響有」(影響がないのにあるとされること)やいくつかの「偽影響無」(影響があるのにないとされること)といった誤った評価もあり,これでは曝露が過大あるいは過小評価されてしまい,異なる研究を正確に比較することは不可能だ。
それにもかかわらず,大部分の研究では,概して自然環境中で見つかった最も高い濃度でも,粒子が1000リットル当たり1~10数個の範囲より低いとしている。実験の濃度と比べ数桁少ないレベルであり,この程度の少量のプラスチックを飲み込んでいる生物は,同じ環境の中に餌となるプランクトンがこの数百,数千倍以上いるのを見つけるだろう。
また,多くの研究は,重量(たとえばミリグラム/リットル)か,海の面積(個数/平方キロメートル)もとにして,濃度を見積もっている。こんな(大雑把な)単位では,実際に海で生物が様々な粒子にさらされている実態を知ろうにも大きな曖昧さが残る。」
バートン教授は,実験によるマイクロプラスチックの曝露量が,あまりにも多く,自然環境の実態からかけ離れたレベルにあることを問題視する。また,扱う単位が異なることによって論文間の比較が難しくなり,自然環境の生物がどういう曝露環境にあるのかわからないとも指摘しているのだ。つまり,研究の焦点がずれていて,実際に起こりうる危険性(リスク)への展開が乏しいと,マイクロプラスチック研究の現状を批判しているようだ。
その批判の矛先は,マスメディアや市民などにも向けられる。
脅威論は,メディアが大きく取り上げ,社会の「害」となる
「マイクロプラスチックが環境に重大な脅威を与えるという研究は,すぐにマスメディアにニュースとして取り上げられ,市民と政策立案者に間違った情報を伝える。実際,マイクロプラスチック脅威論が取り上げられる傾向は,政策決定に悪影響を与えている(たとえば,マイクロプラスチックのごく一部分を占めるに過ぎず,環境の脅威となっていないマイクロビーズを禁止すること)。マイクロプラスチックの大部分は,マイクロビーズではなく,むしろ濃度が低くても有害な影響を与えるポリエステル繊維片である。しかし,環境擁護者からは,ポリエステル繊維の服を禁止したり,砕けて破片に分解するかもしれないプラスチックすべてを禁止したりすべきなどという声は聞かない。」
こうした批判というか非難は,マスメディアとしても,市民としても,なかなか受け入れがたい内容であろう。ニューヨーク・タイムズなどの大手新聞社が投稿を取り上げにくかった,大きな理由はこういう点にあったと推測する。これでは,科学者と市民のコミュニケーションが成り立たない。
マイクロプラスチック汚染より先に対処すべき環境問題がある
バートン教授はさらに研究例の少なさにも矛先を向ける。
「加えて,"ナノプラスチック(ナノ粒子)"(100 µmより小さい粒子)による高濃度の曝露がたくさんありそうなのだが,適切な測定が難しいことから,このテーマに挑む研究はほんどない。この特別小さな粒子は環境リスクかもしれないが,本当のところはわかっていないのだ。最近の論文などによると,ナノプラスチックは,ナノサイズのカーボンや金属化合物と共通する性質が多く,環境中では短時間で凝集することなどが示唆されている。ナノサイズの物質の従来研究から学ぶべきことは多い。
マイクロプラスチックのリスクを決定する作業は,実際のリスク(現実の曝露と悪影響との関係)を分析するものでなければならない。また,現実の環境で観察されるべきものでもある。規制当局や環境保護団体は,重大ではなく,脅威というには疑わしい問題に焦点を当てる前に,富栄養化や貧酸素化,病原体,生息地の崩壊,気温など,普遍的で主要な有害因子について取り組むべきだろう。」
たしかに,マイクロプラスチック汚染以外にも環境問題は多い。しかし,少なくともプラスチック汚染のように実態がわからないという一点だけでも,一般の人には「脅威」であることも事実だ。プラスチックがあふれ,海が汚染され,今後も汚染が続くと予測されている。そのプラスチックがどれだけ,生態系や人類に影響を与えるのかはわかっていない。「わからないこと」は人を不安にする。
急増するマイクロプラスチック汚染は,一般の人たち,それに次世代の人々にとって,富栄養化などと何ら変わらない環境問題だ。社会の懸念に応えることも科学者の役割という考えからすれば,マイクロプラスチック汚染の研究を後回しにしてもいいという見解は市民の理解を得られない。
マイクロプラスチックのリスクは重要な問題だ
バートン教授の見解への反論が,同じ学術誌の「Environmental Science & Technology」(2018年1月26日発刊)に掲載された。米バージニア海洋科学研究所のロバート・ヘイル(Robert C. Hale)教授は,「マイクロプラスチックのリスクは本当に取るに足らないのか?」というタイトルで意見を記した。
ヘイル教授の反論を見てみよう。
「(自然界における)曝露は限定的であるから,マイクロプラスチックのリスクは重要でないと考えるべきだとする見解は受け入れられない。膨大な量のプラスチックが環境に排出されており,プラスチックの断片は今後10年で倍増すると予測されている。これだけの量があれば有害であるといえるし,今後さらに増えるのだ。
高分子化合物は,経年や特性,環境条件からマイクロプラスチックに分解してしまうのは避けられない。バートン教授が指摘する通り,マイクロプラスチックを見積もることさえ,私たちは能力的に不十分である。したがって曝露(量)は実際よりも過大に見積もられることもある。
ただ,マイクロプラスチックで,考慮しなければならないのは,粒子のサイズや濃度だけではない。高分子化合物の構成要素,粒子の形,表面積,濃度,永続性,吸着汚染物質,添加物含有量も,マイクロプラスチックの寿命や毒性影響を左右する。こうした要因を十分に解明することがリスク評価の前提条件である。」
ヘイル教授は,曝露量の見積もりが現時点では不十分であることを認めたうえで,問題はマイクロプラスチックの曝露量だけでなく,その形状など他の多くの要因にもあるとし,それらの研究を促進する必要性を訴える。
「最近の研究で,大量のマイクロプラスチックは,サイズが小さくなり増えていることが確認されている。微小粒子(ナノプラスチック)の研究がほとんどされていないという,バートン教授の指摘は正しい。これらの粒子は,表面積が大きく,化学反応性も高いうえ,食物連鎖のほとんどの段階で摂取されやすい。このため,別のリスクが現れるかもしれない。吸入毒性の観点から考えると,10 µmより小さな粒子は肺の気管などに入り,侵す能力が非常に高い。
多くの科学者(バートン教授を含む)が限られた海域の表面から深海までの範囲に分布するマイクロプラスチックに焦点を当てているが,意外な場所,たとえば,辺鄙な海岸や極域,深海堆積物から多くのマイクロプラスチックが見つかっている。マイクロプラスチックが個々の生物へ与える物理的,化学的な影響に加え,高分子化合物の表面が,岩などこれまでとは違った生物群の生息場所となっていることが報告されている。これらは生態に大きな影響を与えるかもしれない。
ほとんどのプラスチックは,水域ではなく陸域に存在する。しかしながら,陸域にあるマイクロプラスチックの影響にはあまり注意が向けられていない。たとえば,マイクロプラスチックは90%までが排水汚泥に取り込まれている。また,室内でホコリを吸い込むことは,難燃剤などの汚染物質の曝露に至る重要な経路だ。室内のホコリに混じるマイクロプラスチックには,その重さの何パーセント分かの添加剤(化学物質)が含まれているかもしれない。ところが,こうした関連リスクはまだ十分に調べられていない。
加えて指摘するならば,水域のプラスチック問題の解決は,プラスチックの多くを使い,流出元となっている陸地で行われる必要がある。」
ヘイル教授は,ナノプラスチックについての研究の必要性を強調し,また,水域のみならず陸域でも,マイクロプラスチック汚染があり,それらに関するリスクの研究も欠かせないという。さらに水域のプラスチック汚染は陸域の問題であるとも強調している。
「バートン教授は,マイクロプラスチックに関するマスコミ報道の範囲の広さについて批判した。だが,こうした報道があるのは,根っこに,問題に強い関心を持つ市民がいるからと言える。行政機関はこの動きにならう。実際に,この傾向が,マイクロビーズ禁止規則の早期成立や専門家の知見や意見の軽視を懸念する流れを後押ししていると言えるだろう。CDC(米疾病予防管理センター)の最近の様々な助言も「科学的助言に加え,市民社会の一般的な考えの基準や願い」に基づいていることに留意したい。したがって,市民の意見やメディアを無視することは賢明でないのだ。汚染物質問題において,科学者でない人たちに手を差し伸べ,啓発する機会はすべて大切であると考えなければならない。プラスチックごみとマイクロプラスチックを減らすことは,幅広い階層の市民と政治家が支持する目標である。マイクロプラスチックが原因となって起きる毒性リスクは,まだ明確にはわかっていない。だからこそ,マイクロプラスチックの研究を軽視するのではなく,推進する必要があるのだ。」
マスメディアの報道は,市民感覚の「代表」である側面があり,それを蔑ろにすることは,市民の求めに背を向けることにつながる。科学者は,市民への啓発活動をするとともに,未解明な部分が多いプラスチック汚染を追究するべきである。こうしたヘイル教授の主張は,市民社会の中でこそ成り立つ,文化として科学の在り方にも関わり,意義深いと思う。市民の支援なくして科学は進展しない,科学の進展なくして市民生活の改善もないだろう。
(文責:三島勇)